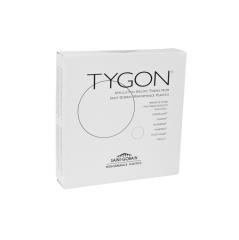チューブ/フィッティング
水路の構成部品。設計と所要部品の見極めが難しい。

チューブの選定
水路の構成は自由度が高い領域である……などというと聞こえは良いが、初心者にしてみればVAULTの出口から見渡すウェイストランドのようなもので、何をどうしたらいいのかわからない危険極まる荒野だと思う。トレンドの最先端はすでにDIY水冷を超えてMOD PCの領域に突入、流行はハードチューブの曲げ加工だとかなんとか。
先を見ているとキリがないので、とにかく「各コンポーネントをチューブで繋ぐ」ことに徹しようと思う。
チューブといってもまた多種多様なわけで、何から決めたものかと途方に暮れる。
フィッティングと対になるので、まずは内径と外径の決定。これは対応製品が最も多いID3/8,OD1/2とする。ヤードポンド法などクソ食らえだと思うのだが、主要コンポーネントが海外製であるためどうにもならない(ドイツ人は13/10mm、12.7/9.5mmなどと表記したりもするが、厳密にサイズが合うのか却って不安になったりする)。
規格に合うチューブの中から選ぶわけだが、こればかりは正直現物に触らないと分からない。
調べた中で評判の高いTygon R3603(E3603)はどうかと思ったら、これが非常に高価。メートル単価が軽く1000円を超える。海外では数割安く売っているところもあるが、15m単位でしか売っていなかったり。
よくよく考えたら、狭いPCケースの中で数個のコンポーネントを接続するだけなのだから、それほど長さが必要になるわけがない。最終的には30~40cmを4本も切り出せば足りるだろう。
というわけで、本組用にTygon E3603を3m、試験用に1.16ドル/ftのチューブを20ftばかり仕入れてみた。
Tygon E3603は評判通り柔らかくしなやかではあるが、これはとりもなおさず曲げた時に潰れやすいことも意味している。安くて硬いチューブの方が適している局面もありそうなので、よくよく注意が必要である。
フィッティングの選定
チューブをコンポーネントに接続するためのフィッティング(継手)。分岐などを別にすれば、コンポーネント×2個必要になる。
ただ、後述のカップリングに置き換える部分があるので、フィッティングそのものの所要数はその分減る。
今回は試験用や予備を見込み、Monsoonの6個セットとKoolanceのバラを4個購入。
一方、経験がないと必要性や所要数が見極められないのが、角度付きのフィッティングだと思う。チューブの曲げに頼るだけでは限界があるので、取り付け部に角度を付けることでチューブの負担を減らすわけだが、これは実際にやってみないと実感が湧かない。
ただ、かなりの確度で必要になるうえ、後から単体で調達しようとすると手間、時間、費用と三拍子揃ってダメージを受けるので、最初から予備としていくつか調達することをオススメしたい。
ちなみに、私は45°と90°の継手を2つずつ用意していたが、全部使い切った。最終的には、干渉発生に伴う引き回しの変更で、90°を4個、45°を1個使うことになった。
カップリングの選定
カップリングとかクイック・ディスコネクタ(QD)などとも呼ばれる部品。
特徴は、シャットオフバルブの内蔵により、クーラントが充填されている状態であってもコネクタを切り離せること(ノンスピル・カップリングと呼ばれる)。漏洩は厳密にはゼロではないが、公称1cc。コネクタに付着した雫をティッシュで拭えばそれで済む程度。
昔、ガスガンを弄っていた頃には同じような機構に大変助けられていたことを思い出し、今回はこれを大々的に導入する事にした。
選定したのはCPC(米Colder社) NS4シリーズ。本来はDIY水冷用ではないが、EKの水冷キット、Predatorシリーズにも採用されている。
調べてみると、個人相手でも販売してくれる販売店を見付けたので、これで行く事に。理由は、EKでの採用実績がありながらも「本来はDIY水冷用ではない」こと。こと狭いジャンルで使われるパーツは、専用品より汎用品を使った方が安上がりであるという経験則からだ。
それでも結構値が張るが、ショップで「DIY水冷用」として購入するよりははるかに安い。それなりに数が必要でもあるので、こうした努力には意味があると思う。
問題は、ネジの仕様がNPTであること。水冷コンポーネントのG1/4とは互換性がないので、変換アダプタを噛ませる必要がある。ところが汎用品に全然見当たらず、制作を発注すると一個950円という値段になってしまうということで頭を抱えることに。
意外にもKoolanceからまさに必要な変換アダプタが出ていたのでこれを調達して事なきを得たのだが、汎用品では需要のない組み合わせだったのだろうか。
クーラントの選定
クーラントも何が良いのか迷う所。
電触という恐ろしい現象がある。PCというより化学の話だが、イオン化傾向の違う金属を導電性のある液体で接続すると腐蝕電流が流れて激しく腐食してしまう。これがPCの中で起こると考えるととんでもない話だ。
もっとも、現在DIY水冷用として販売されているクーラントには大抵電触防止のための成分が添加されているとの事で、過度に気にする必要はないようだ。
水冷PCのえらいひとに聞いてみたところ、「水冷用に売られているもので問題が出たと聞いた事はない。好みで選べば良い」とのこと。
機能面で問題がないならと、Thermaltake C1000 Opaque Coolant Blueを選択。
UVライトで光らせるような予定もないので、そちら方面の機能は不要。不透明なものを選んだのは視認性が高そうだから。一瞬毒々しい赤色も考えたが、無難で涼しげな青色とした。
聞いた話では自動車用のクーラントを使う強者もいるそうで。カー用品店での値段を見ればコストパフォーマンスは別次元と言えそうだが、普通のDIY水冷では1リットル弱くらいしか使わない。超巨大外付けラジエータでも使わない限りはメリットが薄そうだ。